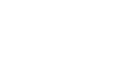1.講習会の内容
Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材料による一体製作など,多くの利点があります。これらの特長を利用した設計は,Design for Additive Manufacturing (DfAM)と呼ばれ,既存製品を圧倒する革新的な製品につながると期待されています。また,DfAMを効率的に進めるには,コンピュータが形状創生するComputational Design (CD)の活用が欠かせません。
本講習会では,DfAMの概念とDfAMの実践に欠かせないCD,そしてCDの代表的な方法として最近,普及が進んでいるGenerative Design (GD)について説明します。
2.開催の動機と講習会の特長
DfAMは比較的新しい言葉でありますが,従来より「3Dプリンターならではの設計」などとして注目されていました。3Dプリンターの特長の一つに複雑形状の製作があるので,DfAMによる設計は複雑になりやすく,アイディアの生成から寸法の計算,モデリングの操作まで全て人が行うには,あまりに煩雑な作業となります。そのため,コンピュータプログラムや人工知能(AI)の力を活用して凡その形状を生成するコンピュテーショナルデザイン(CD)が有効な手段となります。
CDはコンピュータが設計することであり,3D-CADを使って人が設計をするデジタルデザインとは異なります。ジェネレーティブデザイン(GD)は,CDの代表的な方法で,位相最適化をベースにしたGDソフトウェアが3D-CADにバンドルされるようになり,身近に利用できるようになりました。しかし,DfAM, CD, GDの名前だけが広まり,それぞれの概念や有用性,実際の方法などについて,十分に理解されていないように思います。これらの概念とそれぞれの繋がりを知ることで,AMの有用性が深く理解され,新たな技術開発やビジネスのヒントになると考え,本講習会を企画しました。
3.講座の内容
① DfAMについて
AMの特長,DfAMの分類,メタマテリアル,コンプライアントメカニズムなど
② コンピュテーショナルデザイン
アルゴリズミックデザイン,形態認知,美的好み,機械学習など
③ ジェネレーティブデザインの実践
ジェネレーティブデザインのソフトウェア,3D-CADとの連携など
4.日時
2024年9月11日(水)17:00-20:00
5.実施方法
Zoomによるオンラインで行います。
6.講師
講師:舘野寿丈(明治大),加藤健郎(慶應義塾大),中村 翼(オートデスク㈱)
7.参加費
学会員(協賛学会員を含む):10,000円(非課税)
非会員:20,000円(税込)
学生会員:5,000円(非課税)
学生非会員:5,000円(税込)
8.申込み
こちらからお申込みください。
締切:2024年8月23日(金)
9.問合せ先
日本設計工学会事務局 E-mail: jimukyoku@jsde.or.jp