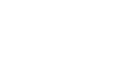ホーム » 「announce」タグがついた投稿
タグアーカイブ: announce
2025年度デザイン塾:設計(デザイン)知のコンシリエンス
日時
2025年7月18日(金)13:00-16:00
会場
オンライン(Zoom)
共催
- 日本機械学会 デザイン科学研究会
- 日本デザイン学会 デザイン科学研究部会
- 日本設計工学会 デザイン科学に関する研究調査部会
- 丸善出版
- デザイン塾
参加費
無料
参加登録
WEBからお申し込みください.https://forms.gle/N45AiZfFz667CLXf7
参加登録締切
7月14日(水)
趣旨
これからの10年~20年で,設計(デザイン)は大きな変革期を迎えます.「量子設計(デザイン)」時代の到来もその1つです.量子コンピュータ,量子暗号システムなど量子技術の設計への応用が始まります.これは,従来とは全く異なる設計環境をもたらし,新たな設計の在りようが求められます.そのため,デザイナーや設計者たちは,これから果敢に立ち向かう挑戦・苦闘のために,今から充分な「そなえ」を仕込んでおく必要があります.
設計知のコンシリエンスは,その「そなえ」の1つです.おさえておくべき設計知は,AIなど先端のデジタル知のみではありません.設計行為の本質を示す基礎理論・方法論の知.これらは今後,設計の体幹として不可欠になっていくでしょう.また,漆工,金工,陶芸などの手工芸が有する「匠」の知.現在の設計は,これらの知を忘れてしまっている気もします.長年により培われてきたこれら達人の知を今こそ見つめなおし,その本質をきたるべき近未来に活かすことも重要ではないでしょうか.
私たちは,現在,設計知のコンシリエンスとして,「現代設計学事典(仮称)」の編纂を進めています.本デザイン塾では,その中間報告を通じて,デザイナー・設計者など日々現場で従事されておられる実務者の方々,多様な領域の研究者の皆様からご意見・ご要望を頂戴し,近未来の設計のあるべき姿について,ともに考える場にできればと考えています.
スケジュール
- 13:00開会司会:佐藤浩一郎(千葉大学)
「『現代設計(デザイン)学事典(仮称)』編纂に向けて」小林秀一郎,大江明* (丸善出版) - 13:05-13:45 「設計知の歴史的変遷と枠組み」松岡由幸*(慶應義塾大学)
- 13:45-14:00 「設計理論・方法論・方法のコンシリエンス」松岡由幸*,加藤健郎(慶應義塾大学),佐藤浩一郎
- 14:00-14:30 「ハードウェア設計知識のコンシリエンス」加藤健郎*,野間口大*(大阪大学),村上存(東京大学),舘野寿丈(明治大学),小林昭世(武蔵野美術大学),佐藤弘喜(千葉工業大学),佐藤浩一郎,大泉和也(東京電機大学)
- (14:30-14:45 休憩)
- 14:45-15:15 「ソフトウェア設計知識のコンシリエンス」細野繁*(東京工科大学),小木哲郎(慶應義塾大学),井上貢一(九州産業大学),松岡慧(香川大学)
- 15:15-15:30 「設計マネジメント知識のコンシリエンス」宮下朋之*(早稲田大学),佐藤弘喜,舘野寿丈,野中朋美(早稲田大学),松岡由幸
- 15:30-16:00 総合ディスカッション
(*は代表発表者)
※お問い合わせ
慶應義塾大学加藤研究室( katolab-secretary-group@keio.jp )までご連絡ください.
デザイン塾HP
2025 年度 見学会(対面)株式会社 コガネイモールド
8月8日 @ 13:00 – 16:30
2025年度見学会(対面)株式会社コガネイモールド
〜主要生産商品:精密樹脂金型・プレス金型・部品加工・成形品の設計および 製作 等〜
1.開催趣旨:
設計コンテスト2025で企画した工場見学を,広くJSDE会員の皆様にも募集することにしました.コガネイモールド様は,金型技術を活用し,将来欲する品物と生産方法をいち早く創りだすことにより,社会に貢献することを経営理念としている会社です.一般的な製作(試作,金型,成形測定)と,依頼者のアイディアベースから一緒に考え,実際のものづくり工法を提供する提案ベースのソリューションサービスを提供しています.
コガネイモールド様は,取引を検討されている企業から小学校の社会見学まで広く工場見学を受け付けており,最新のCAD/CAMおよび最新鋭の工作機械を使用した,樹脂成形金型の製造工程をご覧いただけます.皆様の身の回りにあるプラスチック製品がどのように作られているのか.日本のものづくりを支える金型製作の現場を見学いたします.
*今回の見学会は対面開催 で実施 いたします
*ご同業者の方はお断りさせていただく場合がございます .
2.定員:
先着12 名様とさせていただきます.
3.日時
2025年8月8日(金)13:00-16:30
4.集合場所・時間
・JR 北陸 新幹線 佐久平駅蓼科口 幸せの鐘
・12:30 (現地にはタクシーで 12 分)
5. 見学先:
〒1385 0009 長野県佐久市小田井 1119
TEL 0267 68 0505 / FAX 0267 67 2921
https://kkanagata.co.jp
6.参加資格
本会会員(参加費無料/交通費各自負担)
学生は非会員でも可
7. スケジュール(司会:髙橋)
13:00~13:10 開会の挨拶 内容説明,注意事項
13:10~14:10 コガネイモールド(土村健治様,丸山和生様 ほか)ご挨拶と会社概要・取組 の紹介
14:10~15:40 工場見学
15:40~15:50 休憩
15:50~15:20 質疑
16:20~16:30 終りの挨拶(日本設計工学会代表 )
参加申込・問合せ
申込締切:2025年7月25日(金)
問合せ先:(公社)日本設計工学会 事業部会 講習会担当
TEL:03 5348 6301
Email: jimukyoku@jsde.or.jp
Designシンポジウム2025 講演募集
日本設計工学会 会員の皆様
精密工学会、日本機械学会、日本設計工学会、日本デザイン学会、日本建築学会、人工知能学会の6学会が隔年で共催してきましたDesignシンポジウムが、2025年は人工知能学会を幹事学会として以下の通り開催されます。
各学会の異なる専門の観点からの情報交換や議論の場となっておりますので、多くの皆様のご講演申込をお待ちしております。
開催日
2025年12月2日(火)~3日(水)
会場
慶應義塾大学日吉キャンパス
講演応募締切
2025年8月20日(水)
講演原稿提出締切
2025年10月29日(水)
特設サイト
詳しくは下記のサイトでご確認ください。
・シンポジウムWebサイト: https://d-sym.jp/2025/
・CFPページ(EasyChair): https://easychair.org/cfp/ds2025
【東北支部】東北支部設立50周年記念式典・記念講演会・研究発表講演会講演募集のお知らせ
主催
(公社)日本設計工学会東北支部
共催
東北大学工学部・工学研究科(予定)
開催期間
2025年9月19日(金)~20日(土)
日程
2025年9月19日(金)
13:00~ 記念式典
13:40~ 記念講演会
15:30~ 見学会(NanoTerasu)
18:00~ 記念祝賀会兼技術交流会
2025年9月20日(土)
9:30~ 研究発表講演会(学生優秀発表賞含む),特別講演
会場
東北大学大学院工学研究科青葉記念会館(〒980-0845仙台市青葉区荒巻字青葉6-6)
https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=c&build=03
交通
仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」行「青葉山」駅で下車(乗車時間9分,料金250円)
「青葉山」駅から徒歩約10分,青葉山連絡バスを利用することも可能.
https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/access.html
研究発表講演会
講演募集分野:1. 製品設計,開発,2. 設計法,設計過程,3. 機構,機械要素,4. 解析,設計評価,5. 加工,生産,6. 計測,制御,7. 形状処理,CG,8. 設計・製図教育,9. 企業内技術者教育,10. その他
講演時間:1件20分(内訳:発表15分,質疑討論5分)
申込資格:会員・非会員に係わらず申込可とします.ただし,学生優秀発表賞への申込は会員(東北支部所属の正・賛助・学生)またはその共同研究者とします.
講演申込方法:Googleフォームから講演申込用紙を,ご提出ください.
※googleフォームからの提出には,googleアカウントでのログインが必要です.
申込締切:8月8日(金)
記念講演,特別講演
記念講演(9月19日(金)):矢地謙太郎氏(大阪大学)
講演題目:「新奇設計を実現するトポロジー最適化の今とこれから
〜かたちの交叉を駆動源とするデータ駆動型ジェネレーティブデザインへ〜」
特別講演(9月20日(土)):岩附信行氏(大学改革支援・学位授与機構,東京科学大学,日本設計工学会会長)
講演題目:「設計を学ぶということ」
原稿作成
「講演論文割付見本」 を参考に作成ください(脚注部分は「日本設計工学会東北支部令和7年度研究発表講演会(2025年9月20日)」と記入).
原稿のページ数は,偶数で最大4ページです.原稿提出用のGoogleフォームのURLを講演申込者にお知らせします.
原稿提出締切
8月29日(金)
参加登録料
正会員:4000円
学生員および学生:2000円
非会員:6000円
※記念式典・記念講演会のみ参加される方は無料です.
参加申し込み(外部リンク:イベントペイ)
参加登録期間:8月1日(金)~9月5日(金)
講演論文集はPDFとし,ダウンロードするためのURLを9月5日以降,参加登録済みの方にお知らせします.
付帯行事(見学会,記念祝賀会・技術交流会)
1.見学会
2025年9月19日(金)15:30~16:30~
3GeV高輝度放射光施設 NanoTerasu
定 員:30名程度(定員になり次第締め切ります.)
移動・集合場所:仙台市地下鉄東西線「青葉山」駅南口に集合し,青葉山連絡バスにより移動します.予定時間と経路は次の通りです.
青葉山駅南口(南1)発(15:10)→ NanoTerasu着(15:19)→ NanoTerasu発(17:10)
申込方法:研究講演発表会の参加申し込み先(外部リンク:イベントペイ)から申込ください.
参加費:無料
2.記念祝賀会・技術交流会
2025年9月19日(金)18:00~20:00
会場:TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口(980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2-15)
会費:6,000円(学生2,000円)
申込期間:8月1日(金)~9月5日(金)
申込方法:研究講演発表会の参加申し込み先(外部リンク:イベントペイ)から申込ください.
問合せ先:山口健(東北支部研究発表講演会実行委員会)
TEL:022-795-6897,E-mail:takeshi.yamaguchi.c8@tohoku.ac.jp
2025年度通常総会報告
公益社団法人日本設計工学会 2025年度通常総会報告
日時: 2025年5月24日(土)・25日(日)
会場: 日本大学理工学部 船橋キャンパス
内容: 春季研究発表講演会,特別講演,通常総会,技術交流会,支部長・理事合同会議が開催された.また関連行事として第31回設計フォーラムが併催された.
2025年度通常総会の概要
1. 総会成立宣言
村上副会長より3月末日現在の正会員数,賛助会員数と本日の出席者数,委任状による出席者数が報告され,定款28条の総会成立要件を満たし,かつまた3号議案定款改訂の件の議決条件も満たしており,本総会の成立が宣言された.
2. 会長挨拶
岩附会長より,本日の議事内容について説明の後.事業計画並びに収支予算書は理事会で承認後に内閣府へ提出済であり,本総会ではその内容を報告する旨説明され,合わせて議事進行への協力要請がなされた.
3.議長選出及び議事録署名人選出
定款25条に基づき,岩附会長が議長席に着席後,司会の村上副会長より議事録署名人の選出について説明があり,宮下副会長と舘野理事が選任された.
4.2024年度事業報告
宮川理事より2024年度の事業報告について説明があり,報告通り承認された.
5.2024年度決算報告・監査報告
宮川理事より2024年度の収支計算書,収支計算内訳書,正味財産増減計算書,貸借対照表,財産目録について説明があった.引き続いて荒木監事より「4月30日に事務局にて2024年度収支計算書,収支計算内訳書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録について監査を行った結果,適切かつ正確である」との監査報告がなされ,原案通り承認された.
6.定款改訂
岩附会長より,今般,公益法人法改訂に伴い,外部理事・外部監事の設置が義務付けられた旨の報告があり,同時に当学会として今後の人材育成の観点から,役員増員を図りたく,定款改訂の提案があった.これを受け,宮川理事から改訂内容案の説明があり,提案通り承認された.
7.2025・2026年度役員選出
岩附会長より,先日行われた役員選挙の結果,375通の有効投票があり,投票率について48.3%であった事が報告された.あらためて各候補の名前が読み上げられ,候補者全員が承認された.
8.名誉会員推薦
岩附会長より,候補者「喜成年泰」氏(北陸支部)の推薦理由の説明があり,提案通り喜成年泰氏を名誉員に推挙した.
9.2025年度事業計画・予算計画
宮川理事より,定款39条1項に基づき,2025年度事業計画・収支予算書について報告があった.
10.閉会挨拶
村上副会長より,熱心な審議への協力御礼と共に,今後更なる充実した活動を行いたい旨の挨拶があった.
11.表彰
武藤栄次賞優秀設計賞3件,武藤栄次賞VP賞1件,名誉員の証授与1名,功労賞1名,貢献賞3名の表彰が執り行われた.
春季研究発表講演会
46件の研究発表講演が3会場で行われた.この中では設計開発,表面,トライポロジー,CAD/CAM/CAE,ロボット・メカトロニクスの設計開発,創造性教育と設計教育,計測・安全工学・設計管理,設計理論・方法論,医工学機器の設計開発,機械要素の設計開発,技術伝承・製造責任・工学理論,設計コンテストなどの研究成果が報告されている.また,「自動測定を実現する幾何公差主体の3DAモデルの展望」と題して,第31回設計フォーラムが併催された.更に,「プロダクトデザインの視点から見るヒトとモノの関係」と題して,特別講演が行われた.
支部長理事合同会議
大会2日目の昼時間を使い,新体制の支部長・理事合同会議が懇談的に行われた.出席者は17名+事務局1名の18名で開催された.岩附会長が司会を務め,各部会並びに各支部の活動状況や新年度の活動計画等の報告,本部から支部への要望,支部から本部への要望などについて話し合われた.
技術交流会
5月24日(土)の2025年度通常総会終了後に,2024年度奨励賞・特集企画賞,武藤栄次賞各賞受賞者,MIR賞並びに2024年度秋季大会における優秀発表賞・学生優秀発表賞の各受賞者をはじめ,多数の参加者を迎えて技術交流会が開催された.吉田洋明大会実行委員長,岩附会長の挨拶ののち,MIR賞,優秀発表賞,学生優秀発表賞等の各賞の表彰が行われた.事務局より2025年度秋季大会が11月に長崎にて開催される事,2026年度春季大会は60周年記念大会として開催される旨の報告があった.会場では終始和やかな技術交流の輪が広がり,懇談が行われた.
むすび
今回は日本大学理工学部船橋キャンパスを借用し,多数の参加者を得て,2025年度春季研究発表講演会,設計フォーラム,特別講演並びに総会関連行事を成功裏に終える事ができました.会場の提供から準備・運営に多大なるご協力・ご尽力をいただいた日本大学理工学部ならびに関係者の皆様に深く感謝の意を表する次第です.(前川善太郎 記)
『日本規格協会』標準化と品質管理全国大会2025
持続可能な未来社会をデザインする ―実現のカギはルールメイキングとデジタル革新
開催日
2025年10月14日(火)
場所
都市センターホテル(東京・永田町)
主催団体のWebページ
『日本時計学会』2025年度 特別研究会 AIを利活用するシミュレーション技術の高度化と展望
-材料加工からマテリアルズインフォマティクスまで-
日時
2025年8月1日(金) 13:20~15:00
会場
中央大学理工学部 5号館3階5336号室(東京都文京区春日1-13-27)
主催団体のページ
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容
Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材料による一体製作など,多くの利点があります。これらの特長を利用した設計は,Design for Additive Manufacturing (DfAM)と呼ばれ,既存製品を圧倒する革新的な製品につながると期待されています。また,DfAMを効率的に進めるには,コンピュータが形状創生するComputational Design (CD)の活用が欠かせません。
本講習会では,DfAMの概念とDfAMの実践に欠かせないCD,そしてCDの代表的な方法として最近,普及が進んでいるGenerative Design (GD)について説明します。
2.開催の動機と講習会の特長
DfAMは比較的新しい言葉でありますが,従来より「3Dプリンターならではの設計」などとして注目されていました。3Dプリンターの特長の一つに複雑形状の製作があるので,DfAMによる設計は複雑になりやすく,アイディアの生成から寸法の計算,モデリングの操作まで全て人が行うには,あまりに煩雑な作業となります。そのため,コンピュータプログラムや人工知能(AI)の力を活用して凡その形状を生成するコンピュテーショナルデザイン(CD)が有効な手段となります。
CDはコンピュータが設計することであり,3D-CADを使って人が設計をするデジタルデザインとは異なります。ジェネレーティブデザイン(GD)は,CDの代表的な方法で,位相最適化をベースにしたGDソフトウェアが3D-CADにバンドルされるようになり,身近に利用できるようになりました。しかしDfAM, CD, GDの名前だけが広まり,それぞれの概念や有用性,実際の方法などについて,十分に理解されていないように思います。これらの概念とそれぞれの繋がりを知ることで,AMの有用性が深く理解され,新たな技術開発やビジネスのヒントになると考え,本講習会を企画しました。
3.講座の内容
① DfAMについて
AMの特長,DfAMの分類,メタマテリアル,コンプライアントメカニズムなど
② コンピュテーショナルデザイン
アルゴリズミックデザイン,形態認知,美的好み,機械学習など
③ ジェネレーティブデザインの実践
ジェネレーティブデザインのソフトウェア,3D-CADとの連携など
4.日時
2025年9月16日(火)17:00-20:00
5.実施方法
Zoomによるオンラインで行います。
6.講師
講師:舘野寿丈(明治大),加藤健郎(慶應義塾大),中村 翼(オートデスク㈱)
7.参加費
学会員(協賛学会員を含む):10,000円(非課税)
非会員:20,000円(税込)
学生会員:5,000円(非課税)
学生非会員:6,000円(税込)
8.申込み
こちらからお申込みください。
締切:2025年8月24日(日)
9.問合せ先
日本設計工学会事務局 E-mail: jimukyoku@jsde.or.jp