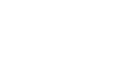ホーム » 「archive」タグがついた投稿 (ページ 2)
タグアーカイブ: archive
【四国支部】令和6年度 支部総会・特別講演会・研究発表講演会のお知らせ
1.支部総会 2025(令和7)年3月13日(木) 2.⽀部研究発表講演会ならびに技術交流会 1)特別講演会 ⽇ 時:2025(令和7)年3⽉13⽇(⽊)13:10〜13:55 会 場:遠隔ライブ⽅式(Zoom) […]
【四国支部】令和6年度研究発表講演会 講演募集
1.開催日時 2025(令和7)年3月13日(木) 2.実施会場 オンライン開催(Zoom) 3.参加費 無料 4.応募資格 発表・連盟者につきまして会員の有無の制約はありません. 5.講演時間 20分間/件( […]
デザイン科学セミナー 新価値創造をもたらす3つの理論,その応用 ~「革新性」と「完成度」を同時に実現する~
1.対象:企画者,デザイナー,設計者,研究者,教育者 2.日時:2025年1月10日(金)13:00-18:00 3.実施方法:Zoomによるオンライン開催 4. 講師:松岡由幸(慶應義塾大学)宮下朋之(早稲田大学)加藤 […]
【四国支部】2024 年度見学会
1.日時 2024 年 12 月 18 日(水) 13:30 開始 2 時間程度を予定 2.見学先 丸井産業株式会社 〒779-1123 徳島県阿南市那賀川町手島榎瀬 42 ※丸井産業株式会社様への個別の連絡はご遠慮 […]
2023年度 論文賞・奨励賞
齊藤 雅博,中村 秀弥 続きを読む
2023年度 The Most Interesting Reading賞
藤田 喜久雄,梶村 典彦,竹井 伸吾,高嶋 毅年,益田 栄壮,平井 真奧 続きを読む
2023年度 武藤栄次賞優秀学生賞
武藤栄次賞優秀学生賞は,武藤工業株式会社元専務取締役武藤栄次氏より本会に寄贈された寄付金を基金とし,設計工学に関連する工業高等専門学校及び大学の各学科あるいはコースの当該年度の卒業生あるいは修了生の内最優秀な学生1名に […]
2023年度武藤栄次賞優秀設計賞
「交流磁場曝露が人体に及ぼす生理学的影響の解明に基づく電気磁気治療器の開発」,綿貫 啓一,石渡 弘美,岡野 英幸,黒沼 典生,目黒 恭夫 続きを読む