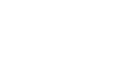ホーム » 「archive」タグがついた投稿
タグアーカイブ: archive
2025年度通常総会報告
公益社団法人日本設計工学会 2025年度通常総会報告
日時: 2025年5月24日(土)・25日(日)
会場: 日本大学理工学部 船橋キャンパス
内容: 春季研究発表講演会,特別講演,通常総会,技術交流会,支部長・理事合同会議が開催された.また関連行事として第31回設計フォーラムが併催された.
2025年度通常総会の概要
1. 総会成立宣言
村上副会長より3月末日現在の正会員数,賛助会員数と本日の出席者数,委任状による出席者数が報告され,定款28条の総会成立要件を満たし,かつまた3号議案定款改訂の件の議決条件も満たしており,本総会の成立が宣言された.
2. 会長挨拶
岩附会長より,本日の議事内容について説明の後.事業計画並びに収支予算書は理事会で承認後に内閣府へ提出済であり,本総会ではその内容を報告する旨説明され,合わせて議事進行への協力要請がなされた.
3.議長選出及び議事録署名人選出
定款25条に基づき,岩附会長が議長席に着席後,司会の村上副会長より議事録署名人の選出について説明があり,宮下副会長と舘野理事が選任された.
4.2024年度事業報告
宮川理事より2024年度の事業報告について説明があり,報告通り承認された.
5.2024年度決算報告・監査報告
宮川理事より2024年度の収支計算書,収支計算内訳書,正味財産増減計算書,貸借対照表,財産目録について説明があった.引き続いて荒木監事より「4月30日に事務局にて2024年度収支計算書,収支計算内訳書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録について監査を行った結果,適切かつ正確である」との監査報告がなされ,原案通り承認された.
6.定款改訂
岩附会長より,今般,公益法人法改訂に伴い,外部理事・外部監事の設置が義務付けられた旨の報告があり,同時に当学会として今後の人材育成の観点から,役員増員を図りたく,定款改訂の提案があった.これを受け,宮川理事から改訂内容案の説明があり,提案通り承認された.
7.2025・2026年度役員選出
岩附会長より,先日行われた役員選挙の結果,375通の有効投票があり,投票率について48.3%であった事が報告された.あらためて各候補の名前が読み上げられ,候補者全員が承認された.
8.名誉会員推薦
岩附会長より,候補者「喜成年泰」氏(北陸支部)の推薦理由の説明があり,提案通り喜成年泰氏を名誉員に推挙した.
9.2025年度事業計画・予算計画
宮川理事より,定款39条1項に基づき,2025年度事業計画・収支予算書について報告があった.
10.閉会挨拶
村上副会長より,熱心な審議への協力御礼と共に,今後更なる充実した活動を行いたい旨の挨拶があった.
11.表彰
武藤栄次賞優秀設計賞3件,武藤栄次賞VP賞1件,名誉員の証授与1名,功労賞1名,貢献賞3名の表彰が執り行われた.
春季研究発表講演会
46件の研究発表講演が3会場で行われた.この中では設計開発,表面,トライポロジー,CAD/CAM/CAE,ロボット・メカトロニクスの設計開発,創造性教育と設計教育,計測・安全工学・設計管理,設計理論・方法論,医工学機器の設計開発,機械要素の設計開発,技術伝承・製造責任・工学理論,設計コンテストなどの研究成果が報告されている.また,「自動測定を実現する幾何公差主体の3DAモデルの展望」と題して,第31回設計フォーラムが併催された.更に,「プロダクトデザインの視点から見るヒトとモノの関係」と題して,特別講演が行われた.
支部長理事合同会議
大会2日目の昼時間を使い,新体制の支部長・理事合同会議が懇談的に行われた.出席者は17名+事務局1名の18名で開催された.岩附会長が司会を務め,各部会並びに各支部の活動状況や新年度の活動計画等の報告,本部から支部への要望,支部から本部への要望などについて話し合われた.
技術交流会
5月24日(土)の2025年度通常総会終了後に,2024年度奨励賞・特集企画賞,武藤栄次賞各賞受賞者,MIR賞並びに2024年度秋季大会における優秀発表賞・学生優秀発表賞の各受賞者をはじめ,多数の参加者を迎えて技術交流会が開催された.吉田洋明大会実行委員長,岩附会長の挨拶ののち,MIR賞,優秀発表賞,学生優秀発表賞等の各賞の表彰が行われた.事務局より2025年度秋季大会が11月に長崎にて開催される事,2026年度春季大会は60周年記念大会として開催される旨の報告があった.会場では終始和やかな技術交流の輪が広がり,懇談が行われた.
むすび
今回は日本大学理工学部船橋キャンパスを借用し,多数の参加者を得て,2025年度春季研究発表講演会,設計フォーラム,特別講演並びに総会関連行事を成功裏に終える事ができました.会場の提供から準備・運営に多大なるご協力・ご尽力をいただいた日本大学理工学部ならびに関係者の皆様に深く感謝の意を表する次第です.(前川善太郎 記)
2025年度 デザイン科学基礎講座 感動と創造
〜心を動かすモノ・コトづくりのために~
1.講座の趣旨:
(1)感動のメカニズム
人はどうして感動するのでしょう?感動は,どのような時に起きるのでしょう?そもそも,人はなぜ感動を求めるのでしょう?そのような感動のメカニズムについて,ここでは,デザイン科学の視点から切り込みます.
(2)感動を生み出す創造
また,ここでは,デザイン科学の基礎理論:AGE思考モデル,デザイン二元論,多空間デザインモデルの3つを用いて,実際の製品開発事例をまじえ,感動を生み出す創造について解説します.
(3)感動マトリクス
さらに,「感動マトリクス」と呼ばれる,感動を生むためのツールとその使い方を紹介します.このツールは,誰でも簡単に使え,心を動かすモノ・コトづくりに役立ちます.
(4)AIを用いた感動の創造法
最後に,AIを用いた感動の創造法を紹介します.あなたとAIの共創をお試しください.
本講座では,感動の本質とそれを生み出す方法論を紹介します.ぜひ,ご参加ください.
2.実施方法:Zoomによるオンライン
3.日時:2025年6月18日(水)13:00-15:30
4. 講師:松岡由幸(慶應義塾大学 名誉教授 早稲田大学 客員教授 デザイン塾 主宰)
5.参加費:(テキスト分を含みます.)
学協会員(共催学協会):8,000円(非課税)
非会協員:15,000 円 (税込)
学生会員:6,000円(非課税)
学生非会員:6,000円(税込)
6.テキスト: 書籍『モノづくり×モノづかいのデザインサイエンス』を配布.
※参加者全員に,ご指定の住所に送付いたします.
7.申込み先:下記formsにて,お願いします.
https://forms.gle/kf1731ZDMSb4fPyy7
締切り: 2025年6月3日(火)
8.問合せ先:デザイン塾事務局
E-mail: mlabsec@googlegroups.com
2025年度 若手・新人設計者,機械設計を学ぶ学生のための形状設計ノウハウ講習会
~熟練設計者の頭の中にある,知恵と工夫を教えます~
1.講習会の内容
熟練設計者の方々から集めた形状設計に関するノウハウを,その正しい使い方とともに紹介します.
①本講習会の意義と設計業務への活かし方
②棒材の形状設計ノウハウ(押出品等)
③板材の形状設計ノウハウ(プレス品,樹脂成型品)
④形状設計ノウハウの本質と修得のコツ
2.開催の動機と講習会の特長
皆さんは,機械設計や製品開発の現場でどのように設計すればいいのかわからず,いろいろ考え抜いた結果,結局,上司や先輩の設計者にアドバイスを受けるしか他に方法がなかった経験はありませんか? 私が企業で設計に従事していた頃には,よくそのようなことがありました.特に新人設計者の時はそうでした.
たとえば,ある金具の設計において,金具の肉厚を増加させれば,強度や剛性は向上します.しかし,それでは材料費が上がり,重量も増加してしまいます.設計経験の少ない新人設計者にはどうしていいのかわからないのです.ビードを設定する,フランジアップを施すなどのノウハウは,学生時代には教わらないのです.
一般に学生時代には,「このような形状」ならば「この程度の強度を有する」という評価法を,力学のなかで学びます.しかし逆に,「この程度の強度を有する」ためには「このような形状」がよいという設計ノウハウについては学んでいないのです.そのため,現在でも,新人や若手の設計者は,上司や先輩からアドバイスをもらい,経験をつむことによって学ぶしかない,のが実状ではないでしょうか.これでは,いつまでも上司や先輩には頭があがらないですよね.
このような背景から,本講習会では,若手・新人の設計者,就職前の機械設計を学ぶ学生に向けて,熟練設計者の頭の中にある形状設計ノウハウを紹介します.
3.日時:
2025年6月11日(水)13:00-15:30
4. 講師:松岡由幸(慶應義塾大学 名誉教授 早稲田大学 客員教授 デザイン塾 主宰)
5.本講習会の特長
● ノウハウがわかりやすい
・形状にノウハウを適用する前(Before)と適用した後(After)の組み合わせを一覧表で紹介します.
・設計現場で用いる専門用語を一覧表で掲示します.
● ノウハウの効果を理解しやすい
・ノウハウの効果を端的に説明します.
・計算結果(FEM解析結果)をわかりやすく図で示します.
● ノウハウが使いやすい
・身近な使用例を紹介します.
・ノウハウの適正な使用条件,不適正な使用条件を,加工法やその他の注意事項とともに,明らかにします.
6.実施方法:Zoomによるオンライン開催
7.参加費(テキスト代を含む):
学協会員(共催学協会):7,000円(非課税)
非会協員:15,000円(税込)
学生会員:5,000円(非課税)
学生非会員:5,000円(税込)
8.テキスト:書籍『形状設計ノウハウ集:熟練設計者の頭の中にある,知恵と工夫を教えます』
※参加者全員に,ご指定の住所に送付いたします.
9.申込み:
https://forms.gle/7nx7XLRYKLFmMSN37
締切り:2025年5月27日(火)
10.問合せ先:デザイン塾事務局
E-mail: mlabsec@googlegroups.com
2025年度見学会(現地での対面開催のみ)コダマコーポレーション株式会社 試作部・加工技術研究所
〜主要生産商品:CAD/CAMシステムの運用による設計ソリューション提供メーカ〜
1.開催趣旨:
コダマコーポレーションは,CAD/CAMシステムの運用による設計ソリューションを提供する企業です.1989年の会社設立以来,日本の製造業の更なる発展を願い,生産性を飛躍的に向上させるために,CAD/CAM/CAEシステムやサービスを提供してきました.
1996年には,3次元統合CAD/CAMシステム「TOPsolidシリーズ」の販売を開始し,導入コンサルティング,システムの構築・サポート,教育や運用コンサルティングを行い,日本のものづくりを支え,多くの企業においての生産性を向上させ,経営的な成果を上げることに貢献しています.
この度は,同社の試作部・加工技術研究所を見学するとともに,企業紹介や同社の取り組みを中心にご講演をいただきます.ぜひ,奮ってご参加下さい.
なお,今回の見学会は現地での対面開催のみとなりますのでご承知おきください.
*誠に恐縮ですがご同業者の方は,ご遠慮下さいますようお願い申し上げます.
2.定員:
2 0名程度
3.日時
2025年6月11日(水)13:00~16:35
4.集合場所・時間
・12:30 JR羽村駅東口タクシー乗り場
5. 見学先:
コダマコーポレーション株式会社 試作部・加工技術研究所(JIS Q 9100、ISO9001認証事業所)
〒205-0002 東京都羽村市栄町3-3-9
TEL 042-570-6891 / FAX 042-570-6892
JR羽村駅(JR中央線青梅特快で約1時間)下車
東口よりタクシーで7分
6.参加資格
本会会員であること(参加費無料).会員の関係者(学生等)の参加を希望される場合はご相談ください.
7. スケジュール(司会:西山)
12:30 JR羽村駅東口タクシー乗り場に集合
12:30~12:50 タクシー相乗りで企業様に移動
13:00~13:10 開会の挨拶,内容説明,注意事項
13:10~14:10コダマコーポレーション代表者様ご挨拶と会社概要•取り組み
14:10~15:30 技術プレゼン 「(仮題)手戻りのない3次元設計の効率化」
15:30~15:40 休憩
15:40~16:30 施設紹介と工場見学及び質疑
16:30~16:35 終わりの挨拶(日本設計工学会代表者,東京EAC代表者)
終了後,タクシーで羽村駅に移動
17:00〜18:30 希望者のみ羽村駅周辺で懇親会を(予定)
参加申込・問合せ
申込締切:2025年5月26日(月)
問合せ先:(公社)日本設計工学会 事業部会 講習会担当
TEL:03 5348 6301
Email: jimukyoku@jsde.or.jp
※ PDF中の申込みページを修正いたしました.(7月7日18時10分)
デザイン科学セミナー 新価値創造をもたらす3つの理論,その応用 ~「革新性」と「完成度」を同時に実現する~
1.対象:
企画者,デザイナー,設計者,研究者,教育者
2.日時:
2025年1月10日(金)13:00-18:00
3.実施方法:
Zoomによるオンライン開催
4. 講師:
松岡由幸(慶應義塾大学)
宮下朋之(早稲田大学)
加藤健郎(慶應義塾大学)
平尾章成(芝浦工業大学)
井関大介(東京造形大学)
佐藤浩一郎(千葉大学)
5.セミナーの内容
デザイン科学は,企画・デザイン・設計という人の創造的な行為に関する知の統合を図ることでその行為の本質を明らかにし,様々な応用を可能にします.
デザイン思考を学んでも,うまくいかないという方や企業にはおすすめです.
本セミナーでは,デザイン科学の基盤をなす3つの理論をわかりやすく紹介します.ぜひ,モノ・コトづくりの現場でご活用ください.
第1部(13:00-13:50)AGE思考モデル(松岡由幸)
~人はなぜ,デザイン・設計できるのか?
第2部(14:00-15:20)デザイン二元論(佐藤浩一郎,宮下朋之)
~革新的で,かつ高い完成度を創造するために
第3部(15:30-17:20)多空間デザインモデルとMメソッド(加藤健郎,井関大介,平尾章成)
~すべてのデザイン・設計に共通する思考の理論とその応用法
総括,Q&A,相談会(17:30-18:00)(松岡由幸,全員)
6.参加費(テキスト代を含む):
共催学会員:40,000円
非共催学会員:50,000 円
学生:30,000円
7.テキスト:
『デザイン科学事典』(丸善),『Design Science』(丸善)
8.申込み:下記formsにて,お願いします.
https://forms.gle/3X4eLzxMSXJ8F8i2A
締切り:2024年12月16日(月)
9.問合せ先:デザイン塾事務局
E-mail: mlabsec@googlegroups.com
【四国支部】2024 年度見学会
1.日時
2024 年 12 月 18 日(水) 13:30 開始 2 時間程度を予定
2.見学先
丸井産業株式会社 〒779-1123 徳島県阿南市那賀川町手島榎瀬 42
※丸井産業株式会社様への個別の連絡はご遠慮願います。
3.日程
13:30 ~ 14:00 会社および工場概要説明
14:00 ~ 15:00 工場見学
15:00 ~ 15:30 質疑応答など
15:30 解散
4.参加費
無料
5.交通
■お車 駐車場に限りがございますので、できるだけ乗り合わせてお越しください。
■JR・バス
JR 牟岐線、「見能林駅」にて下車。阿南高専まで徒歩 10 分
徳島バス、「阿南工専前」にて下車。阿南高専まで徒歩 1 分
※13:10 頃に集合で阿南高専から自家用車に乗り合わせて見学先に向かいます。
6.申込方法
e-mail で表題を「日本設計工学会 四国支部 2024 年度 見学会」と明記して頂き、
氏名、勤務先、連絡先住所、電話番号(携帯電話も)、e-mail アドレス、交通
手段(車、JR・バス)をご記入の上、下記の申込先にお送りください。
7.申込締切
2024 年 12 月 4 日(水)
8.申込先
〒774-0017 阿南市見能林町青木 265
阿南高専 創造技術工学科 機械コース
奥本良博
直通 Tel:0884-23-7108(学校代表 Tel:0884-23-7100)
e-mail:oku@anan-nct.ac.jp
2023年度 武藤栄次賞優秀学生賞
武藤栄次賞優秀学生賞は,武藤工業株式会社元専務取締役武藤栄次氏より本会に寄贈された寄付金を基金とし,設計工学に関連する工業高等専門学校及び大学の各学科あるいはコースの当該年度の卒業生あるいは修了生の内最優秀な学生1名に贈賞するものである.2023年度は下記受賞者に賞状,賞牌,賞品が授与された.(敬称略)
学部生
| 受賞者 | 所属 | 学科・コース名 |
|---|---|---|
| 原田 宏樹 | 日本工業大学 | 機械工学科 |
| 溝口 隼汰 | 長崎総合科学大学 | 工学部 工学科 機械工学コース |
| 池田 尚大 | 岡山理科大学 | 工学部 機械システム工学科 |
| 渡邊 美月 | 東京理科大学 | 工学部 機械工学科 |
| 佐々 響 | 同志社大学 | 機械システム工学科 |
| 渡部 佑星 | 同志社大学 | 機械理工学科 |
| 寺浦 光毅 | 徳島大学 | 理工学部 理工学科 機械科学コース |
| 長谷川 渉 | 神奈川大学 | 工学部・機械工学科 |
| 千田 了 | 公立小松大学 | 生産システム科学科 |
| 谷口 雄一 | 岡山大学 | 工学部 機械システム系学科 |
| 塩月 悠斗 | 佐賀大学 | 理工学部 理工学科 メカニカルデザインコース |
| 山田 麗人 | ハッピーサイエンスユニバーシティ | 機械工学専攻 |
| 矢野 駿太 | 名古屋大学 | 工学部 機械・航空宇宙工学科 |
| 番匠 俊介 | 金沢工業大学 | 工学部 機械工学科 |
| 片山 岳陽 | ものつくり大学 | 総合機械学科 |
| 荒木 俊哉 | 鳥取大学 | 工学部 機械物理系学科 |
| 多田 匠太 | 山形大学 | 工学部 機械システム工学科 |
| 中口 慎也 | 大分大学 | 創生工学科 |
| 菱木 祐斗 | 近畿大学 | 機械工学科 |
| 溝口 智也 | 崇城大学 | 工学部 機械工学科 |
| 沓名 優弥 | 福井大学 | 工学部 機械・システム工学科 機械工学コース |
| 兪 チェ人 | 工学院大学 | 工学部 機械工学科 |
| 岩谷 大樹 | 工学院大学 | 工学部 機械システム工学科 |
| 村井 岳 | 明星大学 | 理工学部 総合理工学科 機械工学系 |
| 松本 武 | 千葉工業大学 | 未来ロボティクス学科 |
| 小野田 楽 | 静岡大学 | 工学部 機械工学科 |
| 早川 泰聖 | 拓殖大学 | 工学部 機械システム工学科 |
| 合田 稜 | 京都大学 | 工学部 物理工学科 |
| 竹本 侑矢 | 名城大学 | 理工学部 交通機械工学科 |
| 篠倉 太郎 | 豊田工業大学 | 工学部 先端工学基礎学科 |
| 吉野 剛瑠 | 長崎大学 | 工学部 工学科 機械工学コース |
| 有賀 純平 | 日本大学 | 生産工学部 機械工学科 |
| 大溝 結菜 | 信州大学 | 工学部・機械システム工学科 |
| 小森谷 沙希 | 電気通信大学 | 情報理工学域Ⅲ類機械システム |
| 大杉 直輝 | 広島工業大学 | 機械システム工学科 |
| 堀 彰汰 | 広島大学 | 工学部第一類 (機械・輸送・材料・エネルギー系) |
| 佐藤 大翔 | 愛知工業大学 | 機械学科・機械工学専攻 |
| 粉室 明弘 | 龍谷大学 | 先端理工学部 機械工学・ロボティクス課程 |
| 小林 祐介 | 東北大学 | 工学部 機械知能・航空工学科 ファインメカニクスコース |
| 髙木 陽年 | 富山県立大学 | 工学部 機械システム工学科 |
| 中島 憲吾 | 大阪大学 | 工学部 応用理工学科 機械工学科目 |
| 若尾 俊吾 | 大同大学 | 工学部 機械工学科 |
| 飯沼 時信 | 東海大学 | 工学部 機械工学科 |
| 橋本 翔太郎 | 日本工業大学 | 先進工学部 ロボティクス学科 |
| 八田 悠翔 | 上智大学 | 理工学部 機能創造理工学科 |
| TSAI HUNG YU | 徳島文理大学 | 理工学部 機械創造工学科 |
| 清水 郁孝 | 湘南工科大学 | 機械工学科 |
| 片倉 琉偉 | 日本大学 | 理工学部 精密機械工学科 |
| 上村 悠貴 | 東京工業大学 | 工学院 機械系 |
| 遠藤 友人 | 室蘭工業大学 | 創造工学科 機械ロボット工学コース |
| 宇井 翔太 | 東京工科大学 | 工学部 機械工学科 |
| 山田 喬 | 東京大学 | 工学部 精密工学科 |
| 茶森 颯太 | 北海道科学大学 | 機械工学科 |
| 古市 彦乃 | 東京理科大学 | 創域理工学部 機械航空宇宙工学科 |
| 氏次 朗 | 近畿大学 | 生物理工学部 人間環境デザイン工学科 |
| 松岳 勇樹 | 慶應義塾大学 | 理工学部 システムデザイン工学科 |
| 堀部 拓海 | 法政大学 | 理工学部 機械工学科 |
| 高橋 風人 | 千葉工業大学 | 機械工学科 |
| 浅野 美月 | 名城大学 | 理工学部 メカトロニクス工学科 |
| 吉井 智哉 | 名城大学 | 理工学部 機械工学科 |
| サントス エリキ | 関東学院大学 | 理工学部 理工学科 機械学系 |
| 岡田 達樹 | 高知工科大学 | システム工学群 知能機械工学専攻 |
| 濱田 起矢 | 東京都市大学 | 理工学部 機械システム工学科 |
| 藤野 清文 | 明治大学 | 理工学部 機械情報工学科 |
| 笠野 真生 | 新潟大学 | 工学部 工学科 機械システム工学プログラム |
| 鈴木 彩花 | 明治大学 | 理工学部・機械工学科 |
| 菅田 康平 | 中央大学 | 理工学部 精密機械工学科 |
| 福居 亮太朗 | 大阪電気通信大学 | 工学部 機械工学科 |
| 重松 良祐 | 九州大学 | 工学部・機械航空工学科 |
| 大場 亮弥 | 埼玉大学 | 工学部機械工学・システムデザイン学科 |
修士
| 受賞者 | 所属 | 学科・コース名 |
|---|---|---|
| 鈴木 瞳 | 金沢大学 大学院 | 自然科学研究科 フロンティア工学専攻 |
| 前海 利空 | 岡山理科大学 大学院 | 工学研究科 機械システム工学専攻 |
| 小西 遥大 | 近畿大学 大学院 | 総合理工学研究科 メカニックス系工学専攻 |
| 榛葉 広之 | 東京理科大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 堀口 栞 | 同志社大学 | 理工学研究科 機械工学専攻 |
| 深津 美薫 | 東京理科大学 | 創域理工学研究科 機械航空宇宙工学専攻 |
| 寺本 ゆう莉 | 金沢工業大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 田中 沙織 | 名城大学 大学院 | 理工学研究科 交通機械工学専攻 |
| 森岡 陽来 | 慶應義塾大学 | 理工学研究科 総合デザイン工学専攻 |
| 山縣 充紀 | 岡山大学 | 自然科学研究科 機械システム工学専攻 |
| 野口 弘希 | 公立小松大学 | サステイナブルシステム科学研究科 生産システム科学専攻 |
| 荒木 海渡 | 佐賀大学 | 理工学研究科 理工学専攻 機械システム工学コース |
| 田中 優太郎 | 崇城大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 西垣 洸希 | 鳥取大学 大学院 | 持続性社会創生科学研究科・工学専攻 |
| 矢吹 宜大 | 山形大学 大学院 | 理工学研究科 機械システム工学専攻 |
| 河村 卓 | 大分大学 大学院 | 工学研究科 工学専攻 |
| 榊原 尚弥 | 福井大学 大学院 | 工学研究科 博士前期課程 産業創成工学専攻 創造生産工学コース |
| 休場 海知也 | 工学院大学 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 下鳥 晴己 | 千葉工業大学 大学院 | 先進工学研究科 未来ロボティクス専攻 |
| 千田 智 | 北見工業大学 大学院 | 工学研究科・工学専攻 機械電気工学プログラム |
| 小峯 響己 | 静岡大学 大学院 | 総合科学技術研究科 工学専攻 機械工学コース |
| 城出 健太 | 京都大学 大学院 | 工学研究科 機械理工学専攻 |
| 西澤 圭悟 | 関東学院大学 大学院 | 工学研究科・機械工学専攻 |
| 堀江 広夢 | 愛知工業大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 坂口 良輔 | 豊田工業大学 大学院 | 工学研究科 修士課程 先端工学専攻 |
| 川原 豪真 | 長崎大学 大学院 | 工学研究科 総合工学専攻 機械工学コース |
| 宮内 惇 | 信州大学 | 総合理工学研究科 工学専攻 機械システム工学分野 |
| 小林 英里奈 | 電気通信大学 | 情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 |
| 吉中 智美 | 神奈川大学 大学院 | 工学研究科 工学専攻 機械工学領域 |
| 西平 健人 | 広島工業大学 | 工学系研究科 機械システム工学専攻 |
| 黄 奕輝 | 広島大学 大学院 | 先進理工系 科学研究科 先進理工系科学専攻 機械工学プログラム |
| 金澤 由宇 | 日本大学 | 生産工学研究科 機械工学専攻 |
| 小林 一景 | 東海大学 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 秋本 真輝 | 早稲田大学 | 創造理工学研究科 総合機械工学専攻 |
| 中山 悠之介 | 龍谷大学 大学院 | 理工学研究科機械システム工学専攻 |
| 渋谷 孝史 | 日本工業大学 大学院 | 工学研究科 機械システム工学専攻 |
| 李 喆 | 富山県立大学 大学院 | 工学研究科 機械システム工学専攻 |
| 近藤 裕哉 | 金沢大学 大学院 | 自然科学研究科 博士前期課程 械科学専攻 |
| 髙橋 成享 | 大阪大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 大谷 友希 | 大同大学 | 工学研究科 機械工学専攻 機械工学コース |
| 長島 健裕 | 法政大学 大学院 | 理工学研究科 機械工学専攻 |
| 金子 拓人 | 湘南工科大学 大学院 | 工学研究科 博士前期課程 機械工学専攻 |
| 川﨑 浩司 | 東京都市大学 | 総合理工学研究科 機械専攻 |
| 安田 萌恵 | 東京工業大学 | 工学院・機械系・機械コース |
| 鄭 盛華 | 東京工科大学 大学院 | サステイナブル工学研究科 |
| 秦 博語 | 東京大学 大学院 | 工学系研究科 精密工学専攻 |
| 臼谷 陸 | 北海道科学大学 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 下村 海斗 | 室蘭工業大学 大学院 | 工学研究科 生産システム工学専攻 機械工学コース |
| 水谷 陽介 | 明星大学 大学院 | 理工学研究科・機械工学専攻 |
| 中村 晃己 | 名城大学 大学院 | 理工学研究科 メカトロニクス工学専攻 |
| 天弘 篤秀 | 名城大学 大学院 | 理工学研究科 機械工学専攻 |
| 本多 詩聞 | 東京大学 | 工学系研究科・機械工学専攻 |
| 浅井 友彰 | 高知工科大学 大学院 | 工学研究科 基盤工学専攻 航空宇宙工学コース |
| 木内 晶基 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院 融合理工学系 エンジニアリングデザインコース |
| 野口 哲平 | 千葉工業大学 大学院 | 工学研究科 機械工学専攻 |
| 清野 匠太朗 | 新潟大学 大学院 | 自然科学研究科 材料生産システム専攻 機械科学コース |
| 神吉 亮輔 | 明治大学 | 理工学研究科・機械工学専攻 |
| 寺山 伊織 | 中央大学 大学院 | 理工学研究科 精密工学専攻 |
| 日髙 雄斗 | 大阪電気通信大学 | 工学研究科工学専攻・制御機械工学コース |
| 辻 航大 | 九州大学 | 機械工学専攻 |
| 小石 智也 | 埼玉大学 大学院 | 理工学研究科 機械科学専攻 |
高専生
| 受賞者 | 所属 | 学科・コース名 |
|---|---|---|
| 高野 晃成 | 石川工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 福家 智己 | 米子工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 秋山 和紀 | 鶴岡工業高等専門学校 | 専攻科生産システム工学専攻 機械・制御コース |
| 幕内 宏斗 | 新居浜工業高等専門学校 | 生産工学専攻 |
| 藤元 優 | 呉工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 永井 稜大 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 栁原 知佳 | 群馬工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 今田 啓斗 | 阿南工業高等専門学校 | 創造技術工学科(機械コース) |
| 佐藤 匠悟 | 大分工業高等専門学校 | 機械工学科 |
| 髙橋 明弥 | 仙台高等専門学校 | 総合工学科・機械・エネルギーコース |
| 岡田 爽汰 | 東京都立産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 生産システム工学コース |
| 野口 和明 | 東京都立産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 機械システム工学コース |
2024年度武藤栄次賞優秀設計賞受賞者 応募要項
下記要領にて2024年度武藤栄次賞優秀設計賞受賞者を募集いたします.提出すべき優秀設計賞申請書は,過度な準備は必要ないものと存じます.会員各位には奮って応募いただきますようお願いいたします.
募集期間
2024年9月1日(日)~12月31日(火)
提出物
優秀設計賞推薦書および付属資料(設計図等)を正本1部,コピー5部ご提出ください.(https://jsde.or.jp/wp/award/から電子ファイルをダウンロード願います.)
提出先
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17
(公社)日本設計工学会庶務会計部会長 宛
郵便または宅配便でご提出ください.
武藤栄次賞優秀設計賞について
質問等
jimukyoku@jsde.or.jp 宛に電子メールにてお願いします.
2024年度武藤栄次賞Valuable Publishing賞 応募要項
下記要領にて2024年度武藤愛次賞Valuable Publishing賞受賞者を募集いたします.提出すべきVP賞推薦書は,過度な準備は必要ないものと存じます.会員各位には奮って応募いただきますようお願いいたします.
募集期間
2024年9月1日(日)~12月31日(火)
提出物
- VP賞推薦書を正本1部,コピー5部ご提出ください.
(https://jsde.or.jp/wp/award/mutoh_vp/から電子ファイルをダウンロード願います.) - 審査査対象となる出版物5冊(審査終了後,ご希望があれば,着払いにて返却致します.)
提出先
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17
(公社)日本設計工学会庶務会計部会長 宛
郵便または宅配便でご提出ください.
質 問 等
jimukyoku@jsde.or.jp 宛に電子メールにてお願いします.