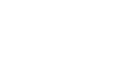ホーム » 事業部会 (ページ 2)
「事業部会」カテゴリーアーカイブ
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材 […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 感動と創造
〜心を動かすモノ・コトづくりのために~ 1.講座の趣旨:(1)感動のメカニズム人はどうして感動するのでしょう?感動は,どのような時に起きるのでしょう?そもそも,人はなぜ感動を求めるのでしょう?そのような感動のメカニズムに […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 新価値創造をもたらす「デザインと設計のあいだ」
~両者のいいとこ取りするモノづくり~ 1.講習会の趣旨本講習会では,「デザインと設計のあいだ」に注目します.デザインと設計の両行為における本質的な相違を示し,その両特徴を統合するための創造の在り方,コツを紹介していきます […]
2025年度 若手・新人設計者,機械設計を学ぶ学生のための形状設計ノウハウ講習会
~熟練設計者の頭の中にある,知恵と工夫を教えます~ 1.講習会の内容 熟練設計者の方々から集めた形状設計に関するノウハウを,その正しい使い方とともに紹介します.①本講習会の意義と設計業務への活かし方②棒材の形状設計ノウハ […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 「不確かさ」に対して頑強な設計の知恵
“高性能化・多機能化”と”安心”のはざまで,設計にできること 1.講座の趣旨:設計者は常に「不確かさ」に悩まされているのではないでしょうか.製品やシステムを設計するうえでは,多くの不確かさが存在します.例えば,寸法や材料 […]
設計コンテスト2025
大学・高専(高専生・学部 生 ・大学院生 )向け 開催趣旨 公益社団法人日本設計工学会(JSDE)は、皆様からご好評を頂きました「設計コンテスト2014」から11年間継続実施してきました「設計コンテスト2025」を開催 […]
2025年度見学会(現地での対面開催のみ)コダマコーポレーション株式会社 試作部・加工技術研究所
〜主要生産商品:CAD/CAMシステムの運用による設計ソリューション提供メーカ〜 1.開催趣旨: コダマコーポレーションは,CAD/CAMシステムの運用による設計ソリューションを提供する企業です.1989年の会社設立以来 […]
2025年度春季大会研究発表講演会
会告 開催日 2025年5月24日(土),25日(日) 会場 日本大学 理工学部 船橋キャンパス 14号館 大会ホームページ https://sites.google.com/keio.jp/jsde2025sp/ 講演 […]
第6回設計工学に関する国際会議(ICDES2025) 講演論文投稿 締切延長のお知らせ
論文投稿締切を延長いたしました。奮ってご投稿ください。 開催日 2025年8月19日(火)~22日(金) 会場 エジプト,アレクサンドリア(アレクサンドリア図書館,及び,エジプト日本科学技術大学) 参加費 一般(事前登録 […]
デザイン科学セミナー 新価値創造をもたらす3つの理論,その応用 ~「革新性」と「完成度」を同時に実現する~
1.対象:企画者,デザイナー,設計者,研究者,教育者 2.日時:2025年1月10日(金)13:00-18:00 3.実施方法:Zoomによるオンライン開催 4. 講師:松岡由幸(慶應義塾大学)宮下朋之(早稲田大学)加藤 […]