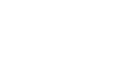ホーム » 「current」タグがついた投稿 (ページ 3)
タグアーカイブ: current
セットベース設計講習会:選好度セットベース設計手法の新たな展開
~規格化された機械要素 設計 ,データマイニング,共分散構造分析への適用~ (公社)日本設計工学会,(特非)セットベースデザイン研究会 共催 1.開催主旨 セット(範囲)ベース設計手法は,新たな設計行為の発想法であると同 […]
2025年度秋季大会研究発表講演会
見学会申込み期限を延長いたしました。2025年9月25日(木) → 9月30日(火) 講演申込み(原稿提出)期限を延長いたしました。2025年9月11日(木) → 9月25日(木) 会告 大会特設ホームページ 大会特設H […]
2025年度デザイン塾:設計(デザイン)知のコンシリエンス
日時 2025年7月18日(金)13:00-16:00 会場 オンライン(Zoom) 共催 参加費 無料 参加登録 WEBからお申し込みください.https://forms.gle/N45AiZfFz667CLXf7 参 […]
2025年度見学会(対面)株式会社コガネイモールド
〜主要生産商品:精密樹脂金型・プレス金型・部品加工・成形品の設計および 製作 等〜 1.開催趣旨: 設計コンテスト2025で企画した工場見学を,広くJSDE会員の皆様にも募集することにしました.コガネイモールド様は,金 […]
【東北支部】東北支部設立50周年記念式典・記念講演会・研究発表講演会講演募集のお知らせ
主催 (公社)日本設計工学会東北支部 共催 東北大学工学部・工学研究科(予定) 開催期間 2025年9月19日(金)~20日(土) 日程 2025年9月19日(金) 13:00~ 記念式典13:40~ 記念講演会15:3 […]
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材 […]
2024年度 武藤栄次賞優秀学生賞
武藤栄次賞優秀学生賞は,武藤工業株式会社元専務取締役武藤栄次氏より本会に寄贈された寄付金を基金とし,設計工学に関連する工業高等専門学校及び大学の各学科あるいはコースの当該年度の卒業生あるいは修了生の内最優秀な学生1名に […]