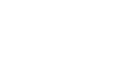ホーム » 「announce-top」タグがついた投稿 (ページ 3)
タグアーカイブ: announce-top
2025年度見学会(対面)株式会社コガネイモールド
〜主要生産商品:精密樹脂金型・プレス金型・部品加工・成形品の設計および 製作 等〜 1.開催趣旨: 設計コンテスト2025で企画した工場見学を,広くJSDE会員の皆様にも募集することにしました.コガネイモールド様は,金 […]
Designシンポジウム2025 講演募集
講演応募締切 2025年9月4日(木)(延長されました) 開催日 2025年12月2日(火)~3日(水) 場 慶應義塾大学日吉キャンパス 続きを読む
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材 […]
論文別刷り料金値上げに関するお知らせ
昨今の人件費・原材料高騰に伴い,論文掲載後に購入いただける別刷り料金に関して 2025年7月1日投稿分 より値上げさせていただきます. 新価格の詳細は,論文投稿のページの「原稿投稿規程・著作権規程・支払いに関する規程」内 […]
2024年度 武藤栄次賞優秀学生賞
武藤栄次賞優秀学生賞は,武藤工業株式会社元専務取締役武藤栄次氏より本会に寄贈された寄付金を基金とし,設計工学に関連する工業高等専門学校及び大学の各学科あるいはコースの当該年度の卒業生あるいは修了生の内最優秀な学生1名に […]
2025年度武藤栄次賞優秀設計賞受賞者 応募要項
下記要領にて2025年度武藤栄次賞優秀設計賞受賞者を募集いたします.提出すべき優秀設計賞申請書は,過度な準備は必要ないものと存じます.会員各位には奮って応募いただきますようお願いいたします. 募集期間 2025年8月1日 […]
2025年度武藤栄次賞Valuable Publishing賞 応募要項
下記要領にて2025年度武藤愛次賞Valuable Publishing賞受賞者を募集いたします.提出すべきVP賞推薦書は,過度な準備は必要ないものと存じます.会員各位には奮って応募いただきますようお願いいたします. 募 […]
訃報 本会元会長 塚田 忠夫先生 ご逝去のお知らせ
2024年12月4日,本会名誉会員で1993年から4年間,本会会長を務められた東京工業大学(2024年に東京科学大学に名称変更)名誉教授塚田忠夫先生が逝去されました.享年86歳でした. 塚田先生は,1964年に東京工 […]