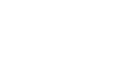機械工学を学ぶ学生のための「形状設計ノウハウ」講習会
~熟練設計者の頭の中にある,知恵と⼯夫を教えます~ 日時:2026年2月23日(月)13:00-16:00 実施方法:オンライン(zoom) 1.受講対象者(受講料:無料) 機械工学関連を専攻した高等専門学校・大学学部 […]
2025年度 「デザイン科学」セミナー
3つの新理論が,⾰新的開発⼒の”体幹”を創り出す︕~ 1.講座の趣旨: ⼤事なことは,およそ理論では決まりません.デザインや設計においても然りでしょう.感性が⼤切です.しかし,プロが第⼀線で活躍し続けるためには,感性だけ […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 M メソッド講習会
今のAIには難しい「意味づけ」から,新たな価値を創り出す~ 1.講座の趣旨: AIが普及する中,人間が得意なこと,人間しかできないことは何だとお考えですか?本講座では,まず,創造行為において,現在のAIが得意なこと,人で […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 CMF デザインサイエンス
模倣からの脱却から,質感のタイムアクシスデザインまで~ 近年,CMF デザインが注⽬されています.CMF とは,⾊(color),素材(material),仕上げ(finish)であり,それらを総合的にかつ丁寧に取り扱 […]
セットベース設計講習会:選好度セットベース設計手法の新たな展開
~規格化された機械要素 設計 ,データマイニング,共分散構造分析への適用~ (公社)日本設計工学会,(特非)セットベースデザイン研究会 共催 1.開催主旨 セット(範囲)ベース設計手法は,新たな設計行為の発想法であると同 […]
2025年度デザイン塾:設計(デザイン)知のコンシリエンス
日時 2025年7月18日(金)13:00-16:00 会場 オンライン(Zoom) 共催 参加費 無料 参加登録 WEBからお申し込みください.https://forms.gle/N45AiZfFz667CLXf7 参 […]
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材 […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 感動と創造
〜心を動かすモノ・コトづくりのために~ 1.講座の趣旨:(1)感動のメカニズム人はどうして感動するのでしょう?感動は,どのような時に起きるのでしょう?そもそも,人はなぜ感動を求めるのでしょう?そのような感動のメカニズムに […]
2025年度 デザイン科学基礎講座 新価値創造をもたらす「デザインと設計のあいだ」
~両者のいいとこ取りするモノづくり~ 1.講習会の趣旨本講習会では,「デザインと設計のあいだ」に注目します.デザインと設計の両行為における本質的な相違を示し,その両特徴を統合するための創造の在り方,コツを紹介していきます […]
2025年度 若手・新人設計者,機械設計を学ぶ学生のための形状設計ノウハウ講習会
~熟練設計者の頭の中にある,知恵と工夫を教えます~ 1.講習会の内容 熟練設計者の方々から集めた形状設計に関するノウハウを,その正しい使い方とともに紹介します.①本講習会の意義と設計業務への活かし方②棒材の形状設計ノウハ […]