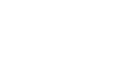ホーム » 2024 (ページ 7)
年別アーカイブ: 2024
訃報 元会長 林 洋次先生 ご逝去のお知らせ

2024年5月16日,本会名誉会員で1997年から4年間本会会長を務められた,早稲田大学名誉教授林洋次先生がご逝去されました.80歳でした.
林先生は,高等学院からずっと早稲田一筋で,1971年に早稲田大学大学院理工学研究科博士課程を単位取得満期退学され,1973年に工学博士(早稲田大学)の学位(博士論文名:非ニュートン流体潤滑の研究)を取得して4月1日より研究室を立ち上げられ,2014年のご定年まで在職45年間(1968年4月1日より早稲田大学助手)早稲田大学にて教育・研究に勤められ,ご退職と同時に同大学より名誉教授の称号が贈られました.この間,1979年より1年間英国のLeeds大学に在外研究員として赴任されています.
ご専門はトライボロジー,機械設計です.トライボロジーでは現象の真実を解き明かすために常に独創的で斬新な実験装置を開発し,制御からデータ取得までを独自のメカトロニクスで行う一方,計算力学の草分けとして研究室内に数十台の計算機を動かしてスパコンにも勝る解析も実現してきました.機械設計では,これらの実用設計の経験を活かし,長年早稲田大学の機械設計教育に携わるとともに,我が国を代表する機械設計の教科書を執筆,改訂して早稲田大学だけでなく多くの機械系教育機関で採用され,機械設計教育の標準となっています.
林先生は,初対面の時に割と個性的で強烈なイメージを抱かせましたが,長い学会活動の接点で頂いたお話を総合すると,すべてに興味が尽きない方と申し上げるしかありません.ご家庭では家族を大切にされ,奥様やお子様のお名前を伺うことも多く,ご趣味というよりセミプロ級のフラメンコギター弾きで,早稲田大学のマンドリンクラブの楽部長でもありました.楽器は研究対象にもなり,共鳴板の振動解析や自動演奏ロボットの開発も手掛けました.
本会には1987年に入会され,多くの部会・委員会で活躍されました.特に出版部会においては,校閲業務の停滞を組織改革して立て直すなど,正義を貫く姿勢が思い出され,出版部会長などを経て会長を務められました.2014年から名誉会員として学会を見守っていただいてきました.お弟子さんの本会前会長富岡淳先生が約2週間前の2024年5月1日にご逝去されたことはさぞ残念に思われていたことと存じます.
林先生のご逝去にあたり,心より哀悼の意を表し,ご冥福をお祈りしますとともに,謹んで会員各位にお知らせいたします.
訃報 前会長 富岡 淳先生 ご逝去のお知らせ

2024年5月1日,本会で会長をつとめられた,早稲田大学教授富岡淳先生がご逝去されました.65歳でした.
富岡先生は,1983年に早稲田大学理工学部機械工学科を卒業され,1989年に同大大学院博士後期課程を修了し,工学博士の学位を授与されました.その後,早稲田大学理工学部の助手,専任講師,助教授を経て,2000年4月より,同大理工学部教授をつとめられていました.またこの間,1991年~1993年にはカリフォルニア大学サンディエゴ校にて,1998年~1999年にはピッツバーグ大学にて,客員研究員をつとめられました.
軸受,シールなどの機械要素のトライボロジーに関する諸問題をご専門とされ,粘弾性流体潤滑の研究,超高速回転用の気体軸受の研究,ジャーナル軸受の動特性の研究,血液レオロジーと溶血特性の研究などに興味をもち,数々の成果を残されました.特に,血液密封用メカニカルシールを開発され,国産初の体内植込み型補助人工心臓システムの実用化に大きく貢献されました.2022年には,ディンプル付きスラスト軸受の研究において,本会の論文賞も受賞されました.
また富岡先生は,長年にわたり,早稲田大学の設計・製図教育を担われており,近年は,『役にたつ機械製図』や『機械製図入門』など,さまざまな学習者を対象とした教科書の執筆にも携わられていました.
本会には1993年に入会され,多くの部会・委員会で活躍されました.2007年からは理事,副会長といった役職を歴任し,2019年からは4年間会長をつとめられました.コロナ禍においても,学会活動の早期正常化,ICDES2020のオンライン開催など,強いリーダーシップで本会をリードされました.2023年からは監事として,引き続き本会の運営に携わっておられました.このように長年にわたり,本会の礎を築いてこられた先生を失いましたことは,誠に残念でなりません.
富岡先生のご逝去にあたり,心より哀悼の意を表し,ご冥福をお祈りしますとともに,謹んで会員各位にお知らせいたします.
2023年度秋季研究発表講演会優秀発表賞,学生優秀発表賞
2023年9月22日(金)~23日(土)日本大学工学部において開催された秋季大会研究発表講演会における講演聴講者の推薦投票結果に基づき,優秀発表賞4件,学生優秀発表賞3件が選定され,2024年5月18日(土),法政大学 小金井キャンパスで開催された2024年度春季大会研究発表講演会技術交流会の席上にて贈賞式が行われた.(敬称略)
優秀発表賞
- 岩附信行(東京工業大学)
講演:「2連節の出力角度限界を指定する総合と多指節指機構への応用」 - 川本貴志(東京貿易テクノシステム)
講演:「物理エンジンを用いた眼鏡着装シミュレーション」 - 大泉哲哉(元仙台高等専門学校)
講演:「JrDr育成塾での3DCAD利用したEVエコラン用モータ開発」 - 西駿明(東北大学)
講演:「活性炭あるいは食塩を添加したゴム材料を活用した耐滑靴底の開発」
学生優秀発表賞
- 太田晴輝(早稲田大学・院)
指導教員:宮下朋之(早稲田大学)
講演:「電気自動車用モータの可変PWM制御に関する研究」 - 宮部拓希(名城大学)
指導教員:大藏信之(名城大学),鈴木昌弘(名城大学)
講演:「臨海レイノルズ数付近の球に働く流体力の挙動と球周りの圧力分布」 - 石山泰成(鶴岡工業高等専門学校)
指導教員:宍戸道明(鶴岡工業高等専門学校)
講演:「自立走行型運搬車の指定経路走行における精度検証」
『日本時計学会』2024年度 見学会
『日本規格協会グループ』標準化と品質管理全国大会2024
日時
2024年10月7日(月)
場所
都市センターホテル(東京・永田町)
参加費
Ⅰ.維持会員にご加入いただいている場合
ご加入1口につき 1名様無料,口数を超えるお申込み 5,500円(税込)/1名様
Ⅱ.一般のお申込みの場合
11,000円(税込)/1名様
主催団体のWebページ
【九州支部】2024年度 総会・特別講演会・研究発表講演会のお知らせ
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます.
九州支部 2024年度(第57回)総会・特別講演会・研究発表講演会を下記のように開催します
2024年度 総会
会場: 九州大学大橋キャンパス 3号館321室(福岡県福岡市南区塩原4-9-1)
日時: 2024年 6月 1日(土) 13 : 00~13 : 40
2024年度 特別講演会
題目: 船舶の静粛化設計について ~大型客船から海洋研究船まで~
講師: 長崎総合科学大学 本田 巌 氏
会場: 九州大学大橋キャンパス 3号館321室(福岡県福岡市南区塩原4-9-1)
日時: 2024年 6月 1日(土) 14 : 00~15 : 00
2024年度 研究発表講演会
会場: 九州大学大橋キャンパス 3号館321室(福岡県福岡市南区塩原4-9-1)
日時: 2024年 6月 1日(土) 15 : 10~16 : 50
- 電機・電子製品のための脱炭素化設計の提案
戸水 晴夫(SDI Japan) - リスクベース設計の基礎となる行動特性の測定(第3報)
堀田源治(九工大),宗澤良臣(広島工大),桐山聡(鳥取大),石川洋平(有明高専),
堀田孝之,坂本英俊(元同志社大) - 聴覚障害者の工作機械操作における支援技術
竹田 雄祐(崇城大) - 機巧図彙を題材としたSTEAM教材開発
渡邊悠太(久留米高専),常木佳奈
学会誌『設計工学』 Vol.59, No.6 2024
特集: 設計における自然言語処理技術の活用(2)
解説
仕様書や不具合報告書などのテキスト情報からの設計知識の獲得
青山 和浩, 239
先端半導体における高度設計・技術融合と技術経営戦略(AI/自然言語処理の活用事例)
岡本 和也, 248
大規模言語モデルを用いた上流設計とDfX学習の支援
原 辰徳, 川村 泰世, 太田 順, 259
分散表現に基づく概念距離の評価と設計概念生成支援
野間口 大, 266
論文(J-STAGEに掲載)
グリース潤滑された小型玉軸受のトルク特性に関する研究(小径玉軸受608のトルク現状調査)
野口 昭治, 東 正浩, 堀田 智哉, 275
生物を模倣した角筒を有するハニカムコアの面外圧潰特性
BEN YUE, 石田 祥子, 斉藤 一哉, 大久保 洋志, 287
Design for Additive Manufacturing (DfAM)とComputational Design講習会
1.講習会の内容
Additive Manufacturing (AM)とは,3Dプリンティングとして知られる積層造形法により部品や製品を製作することです。AMには,従来の製造方法では困難な軽量構造・内部構造の製作,複数材料による一体製作など,多くの利点があります。これらの特長を利用した設計は,Design for Additive Manufacturing (DfAM)と呼ばれ,既存製品を圧倒する革新的な製品につながると期待されています。また,DfAMを効率的に進めるには,コンピュータが形状創生するComputational Design (CD)の活用が欠かせません。
本講習会では,DfAMの概念とDfAMの実践に欠かせないCD,そしてCDの代表的な方法として最近,普及が進んでいるGenerative Design (GD)について説明します。
2.開催の動機と講習会の特長
DfAMは比較的新しい言葉でありますが,従来より「3Dプリンターならではの設計」などとして注目されていました。3Dプリンターの特長の一つに複雑形状の製作があるので,DfAMによる設計は複雑になりやすく,アイディアの生成から寸法の計算,モデリングの操作まで全て人が行うには,あまりに煩雑な作業となります。そのため,コンピュータプログラムや人工知能(AI)の力を活用して凡その形状を生成するコンピュテーショナルデザイン(CD)が有効な手段となります。
CDはコンピュータが設計することであり,3D-CADを使って人が設計をするデジタルデザインとは異なります。ジェネレーティブデザイン(GD)は,CDの代表的な方法で,位相最適化をベースにしたGDソフトウェアが3D-CADにバンドルされるようになり,身近に利用できるようになりました。しかし,DfAM, CD, GDの名前だけが広まり,それぞれの概念や有用性,実際の方法などについて,十分に理解されていないように思います。これらの概念とそれぞれの繋がりを知ることで,AMの有用性が深く理解され,新たな技術開発やビジネスのヒントになると考え,本講習会を企画しました。
3.講座の内容
① DfAMについて
AMの特長,DfAMの分類,メタマテリアル,コンプライアントメカニズムなど
② コンピュテーショナルデザイン
アルゴリズミックデザイン,形態認知,美的好み,機械学習など
③ ジェネレーティブデザインの実践
ジェネレーティブデザインのソフトウェア,3D-CADとの連携など
4.日時
2024年9月11日(水)17:00-20:00
5.実施方法
Zoomによるオンラインで行います。
6.講師
講師:舘野寿丈(明治大),加藤健郎(慶應義塾大),中村 翼(オートデスク㈱)
7.参加費
学会員(協賛学会員を含む):10,000円(非課税)
非会員:20,000円(税込)
学生会員:5,000円(非課税)
学生非会員:5,000円(税込)
8.申込み
こちらからお申込みください。
締切:2024年8月23日(金)
9.問合せ先
日本設計工学会事務局 E-mail: jimukyoku@jsde.or.jp